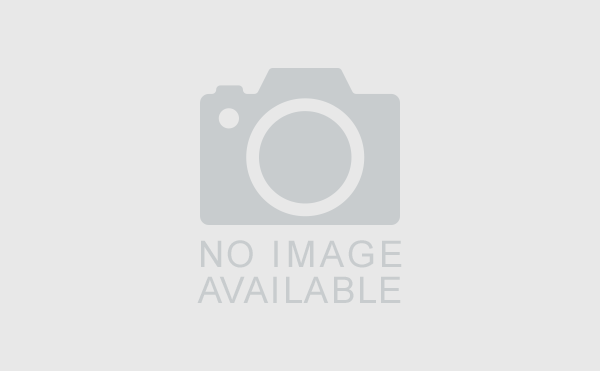低利用魚
« Back to Glossary Index
低利用魚 とは、さまざまな理由から人に食べられる機会の少ない魚のことです。
理由としては、例えば以下のようなことが挙げられます。
・漁獲量が少なすぎる、もしくは多すぎる
・サイズが大きすぎたり小さすぎたりと規格外、もしくは形状(毒やトゲがあるなど)によって、保管やさばくのに手間がかかる
・知名度が低くさばき方などの知識が浸透していない
・特定の地域でのみ食べられていて全国的には知られていない など
低利用魚の中には、獲れるのにまったく使われない「未利用魚」も含まれます。
こうした低利用魚や未利用魚の発生は、約3700種類とたくさんの魚が生息する豊かな日本の海だからこそ起こることともいえます。しかし、せっかく獲れたのに廃棄せざるを得なかったり、網にかかってしまった低利用魚だけを取り除く作業が大変だったりと、海の資源の無駄や漁業に従事する人たちの負担になっています。
SDGs 目標14「海の豊かさを守ろう」の達成には、こうした低利用魚や未利用魚の問題にも目を向ける必要があります。
昨今は、小さすぎる魚がかからないよう網目の大きな漁網を使用したり、加工業者が低利用魚も含めて獲れた魚をまとめて買い取って加工したり、低利用魚のレシピを開発したりと、さまざまな工夫がされています。
※参考:魚食普及推進センターホームページ
※2024年6月現在の情報に基づいて執筆されたものです。その後、変更されている可能性もあります。予めご了承ください 。

お問い合わせ
ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください