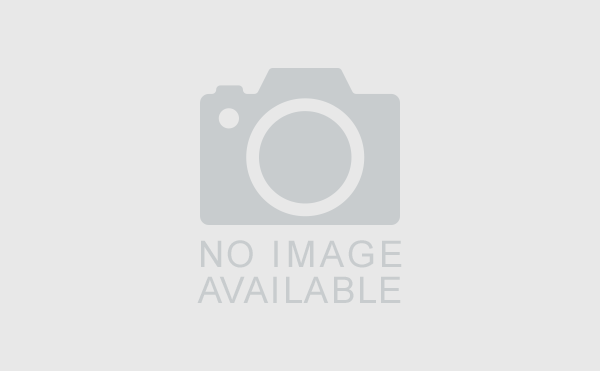生物多様性
生物多様性 とは、さまざまな種の生物や、さまざまな生態系が豊かに存在していることを表す言葉です。
1992年の地球サミット(国連環境開発会議)で採択された「生物多様性条約」では、生態系(森林、河川、サンゴ礁など)、種(動物、植物、微生物など)、遺伝子(同じ種でも異なる遺伝子を持ち、形や模様などが異なる)の3つのレベルの多様性があると定義しています。
生物多様性を守ることは、SDGsのゴール14やゴール15に設定されているように、社会を持続可能なものにするために必要なことであり、人間を含む地球上すべての生物が暮らしていくために欠かせないことです。
日本において
生物多様性国家戦略2023-2030
日本では、2023年に、「生物多様性国家戦略2023-2030」が策定されています。2022年12月にCOP15で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」に対応した、日本の生物多様性保全に関する国の基本的な計画です。2030年までに生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイチャーポジティブ」の実現を目指しています。ネイチャーポジティブ実現のため、社会全体で生物多様性を保全・回復する社会への変革を目指し、生物多様性損失と気候変動という二つの危機への同時解決を目指しています。
その1つの目標として、30by30 があります。
ネイチャーポジティブ経済移行戦略
また、ネイチャーポジティブの実現に資する経済社会構造への転換を促すため、2023年3月に閣議決定され、2024年3月に「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」が策定されています。生物多様性を保全・回復させる「ネイチャーポジティブ」な経済社会を2050年までに実現することを目指しています。
そのために、企業、金融機関、自治体、NGOなど、多様な主体が連携して取り組みを推進しています。
2つの戦略の関係性
「生物多様性国家戦略2023-2030」は、2030年までに生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイチャーポジティブ」の状態を目指しています。これは、現状からの脱却を意味し、生物多様性の減少傾向を食い止め、回復に向かわせるというものです。
一方、「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」は、2050年までに「ネイチャーポジティブ」な経済社会を実現することを目指しています。これは、社会全体の変革を意味し、経済活動が生物多様性を保全・回復するよう社会システムを構築するというものです。
2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復傾向に転じさせ、2050年までに社会経済全体を持続可能なものに変革するという、二段階の目標を設定しているといえます。そのためにも、まずは、集中的な対策を行い、なんとしても2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復傾向に転じさせられるようにする必要があります。
具体的な取組内容
より、実感がわくよう、下記の情報もご覧ください。
環境省の環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書における「第2章 生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組」
※2025年4月の情報に基づいて執筆されたものです。その後、変更されている可能性もあります。予めご了承ください。

お問い合わせ
ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください